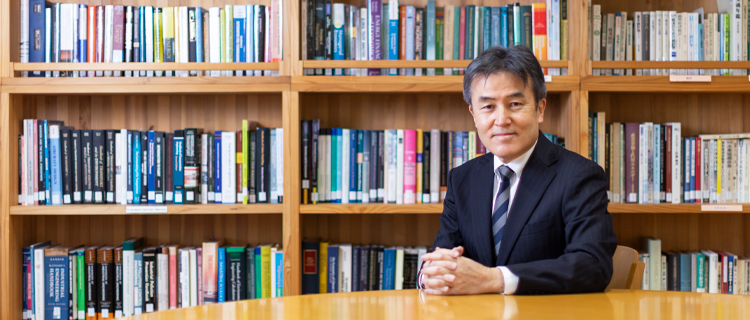「無人島を見つけて、自分の旗を立てよ」研究留学を決意させた恩師のひと言。
今、世界の多くの国と地域、企業が“脱炭素”へと大きく舵を切っている。日本政府は2020年10月、「2050年までに温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする」と宣言、続いて12月に発表された「ガソリン車ゼロ目標(2030年代半ばから新規販売を制限)」は、少なからぬ反響をもって迎えられた。頻発する異常気象の原因の一つとされる地球温暖化。その対策は明確な数値目標と方策、行動によって推し進めるフェーズにきた。私たちは変革の渦中にいるといっても過言ではないだろう。
地球環境問題は1992年の地球サミット(環境と開発に関する国際会議)を契機に大きな進展をみせるようになった。日本では1993年に環境基本法が成立、ようやく“持続可能な発展”への道筋をつけた。地球環境保全が人類共通の課題であると共有されてはいたが、その対策は緒に就いたばかりの時期、スマートシティやインダストリアル・エコロジー(産業生態学)といった次世代の社会・産業界の姿、その具現化について海外の研究者コミュニティと積極的に意見を交わしていたのが中田俊彦教授である。
少し経緯を振り返る。
「私のバックグラウンドは機械工学です。修士課程修了後、電気事業の研究機関で火力発電用エンジンの研究に携わっていました。幸いにも成果も挙がり、充実感がありましたし、若手ホープの一員として名を連ねることもありました。キャリアの見晴らしは良好でしたが、このまま歳を重ねていって、自分自身がワクワクと心躍るような仕事ができるのか、という憂慮を抱えるようになったのです」。そして転職。母校に戻り、助教授(当時)の職を得たのが32歳の時。祖父(農学部教授)、父(公社の研究者から農学部教授)と、奇しくも三代続けて大学での研究/教育を担うこととなった。
大学での研究は「自分が真に興味を持てること」に取り組もうとテーマを模索するものの、それまでの専門分野を超えて見出すことは容易なことではなかった。何も持たぬまま、原野に放たれた心持ちだった。一方で、研究の成果・知見を論文に編み、世に問う姿勢も強く求められた。もちろんこれは研究者としての使命と責務だ。「私はのんびり構えすぎていたようです」と回顧する中田教授。常日頃、何くれとなく目を掛けてくれた年長の教授から、こう諭される。――中田君、君の論文を見たよ。僕はこういうものを読みたいわけじゃない。君はまだ誰も上陸していない無人島を見つけて、自分の旗を立てなければならない。島のスケールは問わない。ただ新しい世界をつくればいい――
それから数カ月後、中田教授の姿は、アメリカ合衆国カリフォルニア州リバモアにあった。フルブライト奨学金を得て果たした研究留学。米国屈指の国立研究所で、自身の研究テーマが鍛えられることとなる。